口腔機能管理研修会(病院向け)
1.挨 拶 動画①
2.講 演
1)診療報酬改定方針に見る 多職種連携による医学的・経済的メリットについて 動画② 配布資料
講師:丹沢秀樹千葉大学大学院医学研究院名誉教授(50分)
2)~医科歯科連携のための 口腔と全身疾患の基礎知識~
総論 口腔と全身疾患の基礎知識 動画③
各論 1 口腔と腸内の細菌叢:その類似点と相違点 動画④ 配布資料
各論 3 ここまでわかった歯周病と難治性全身疾患 動画⑥ 配布資料
講師:落合邦康日本大学 特任教授(4講演)

近年、“慢性炎症性疾患・歯周病”がさまざまな難治性全身疾患のリスクになることが各国の医学、自然科学の専門誌で報告されています。口腔の全身疾患に及ぼす影響が科学的に解明されるにしたがい、医療における歯科医療の役割は大きな注目を浴びております。う蝕という硬組織疾患の治療を中心に発展した歯科医学は、咬合機能回復のための修復技術と材料開発(入れ歯づくり)が最優先課題として発展してきました。さらに、口腔はその特殊性から異分野の研究対象とはなり得ませんでした。また、う蝕や歯周病は直接の死亡原因にならないと考えられ、一般からも口腔疾患は軽視されがちでした。しかし、高齢化社会を背景とした要介護者の増加、周術期・終末医療における専門的口腔ケアの重要性が認識されるようになりました。また、医療費問題という喫緊の課題に対し、歯科医療の果たす役割が再認識されています。これからの歯科医療は、全身疾患予防を視野に入れ、医科を中心とした異分野との連携が必須となると思います。
われわれは「新たな視点で全身から口腔を俯瞰し、それらの結果を元に口腔から全身疾患を考える」という理念「歯学的医学」に基づき研究を続けてまいりました。その結果、歯周病原菌によるHIVの再活性化とAIDS発症、ガン関連ウイルスのEBV再活性化、口腔細菌によるインフルエンザの感染促進と重症化、そして、がん細胞の転移・促進。さらに、口腔ケアによる高齢者の誤嚥性肺炎予防法などの成果を得ました。これらの研究結果から、口腔と全身疾患の関連性をより明確にし、血液を介して「口腔の情報は全身に伝わり、全身の情報は口腔に伝わる」ことを各方面に情報発信してまいりました。
日本細菌学会の祖・北里柴三郎博士は、「医学の究極の目的は予防に有り」といわれました。口腔も例外ではありません。全ての歯科医療従事者はこれらの事実を認識し、口腔の知識のみならず、口腔を取り巻く環境、つまり、全身の生理機能や加齢変化、そして、免疫など関連領域における専門性の高い総合内科医的な視点を持つことが重要と考えます。また、直面している医療費問題解決には、科学的根拠に基づいた歯科医療と口腔ケアの重要性、つまり、「健康長寿における口腔の重要性」を医科・歯科、さらには行政と連携し、広く国民に周知するための啓蒙活動が重要になると思います。
本講演内容は以下の4つの部分から構成されております。必要とされる部分からご覧いただけると幸いです。
総論 口腔と全身疾患の基礎知識
各論 1 口腔と腸内の細菌叢:その類似点と相違点
各論 2 う蝕と歯周病、口腔と免疫
各論 3 ここまでわかった歯周病と難治性全身疾患
落合邦康 略歴 :
1973年; 日本大学農獣医学部 (現:生物資源科学部) 獣医学科卒業
1975年; 日本大学・松戸歯科大学・助手 (細菌学)
1978 ~ 80年; Alabama大学Birmingham校 Medical Center博士研究員
(微生物学、免疫学、生化学分野)
1987年; 日本大学・松戸歯学部・講師専任扱い(細菌学)
1994年; 日本大学・松戸歯学部・講師 (細菌学)
2000年; 明海大学・教授、歯学部 (口腔微生物学)
2005年; 日本大学・教授、歯学部 (細菌学)
同総合歯学研究所・教授 (生体防御部門)
2016年; 日本大学・特任教授、 現在に至る。
3)口腔ケアの手技(寝たきりの方、気管切開の方の口腔ケア)について 動画⑦
講師:平山幸子氏(船橋中央病院歯科口腔外科 歯科衛生士)(30分)
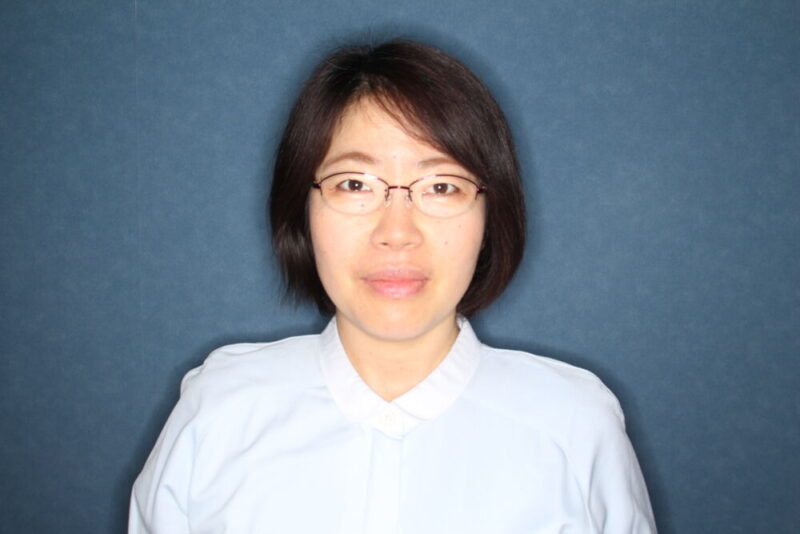
超高齢化社会を迎え、疾患のある高齢者の療養の場は病院から自宅へと移行し、在宅での療養生活を支えるために医療や福祉、行政や地域の住民が一緒に取り組む包括ケアシステムの構築が急務となってきています。介護を必要とされる方は様々な職種のサービスを受けています。それぞれが専門分野を活かして協働し患者様の生活機能を支えるためには、患者様のQOLが保障されるように医療専門職として対応していくことが重要です。
また、近年では長期療養型施設でみられる要介護高齢者の誤嚥性肺炎を医療・介護関連肺炎(NHCAP)と呼んでいますが、これに関しても口腔ケアが重要なことは言う迄もありません.
われわれが日々行っている器質的口腔ケアは一般的なものですが、その主な流れは①体位を整える ②口腔内の観察 ③ケア前の湿潤 ④ブラッシング ⑤舌・粘膜の清掃 ⑥ケア後のチェック ⑦保湿となります。
まず、体位を整えることは垂れ込みによる誤嚥を防ぐ目的と、術者が無理のない姿勢で適切な口腔ケアを行うために必須です。また、口腔内観察は口腔内の状態によって必要とする口腔ケア内容が変わってくることも多いため、口腔ケアの中でも重要なステップとなります。次いで口腔内を湿潤させた後、歯ブラシなどを使ってプラークを除去します。粘膜の清掃の対象として見落とせないものは舌苔と剥離上被膜で、その除去に注意します。口腔内の清掃が終了した後は、出血などがないか全体をチェックし、確認後に保湿剤を口腔内全体に薄く塗布します。
気管挿管患者の口腔ケアは病棟の看護師と連絡を取り、挿管チューブと固定を左右で交換するタイミングに合わせて行うようにしています。この場合、病棟看護師に立ち会ってもらい患者様の情報を共有することが必要で、口腔ケアの継続には看護師・介護士・歯科衛生士が積極的にお互いの情報を交換しながら行うことが重要となります.
急性期病院での入院期間は短期間ですが、その後、ご自宅や施設へ戻られる患者様の良好な予後の継続のために地域連携を図ることが急性期病院のもう一つの重要な役割であり、今回はこれらの経験を通して得られた若干の知見を発表させて頂きたいと考えています.
略歴
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 歯科口腔外科 平山幸子
平成 5年 3月 医療法人田島学園東京医学技術専門学校歯科衛生士科卒業
平成 5年 4月 社会保険船橋中央病院歯科口腔外科 歯科衛生士
平成 26年 4月 独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院歯科口腔外科
歯科衛生士
平成 26年 5月 独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院歯科口腔外科
主任歯科衛生士
所属学会
日本歯科衛生士会・千葉県歯科衛生士会
日本障害者歯科学会
日本口腔ケア学会
臨床関連資格
日本障害者歯科学会 認定歯科衛生士
日本口腔ケア学会認定資格 4級
臨床関連研修
スウェーデン イエテボリ大学歯周病科研修 歯科衛生士コース
講演・論文掲載・学会発表など(最近2年間)
千葉県歯科医学会誌県立衛生保健大学講義 2019.9 2020.9
院内クリニカルカンファレンス 2019.12.
在宅歯科保健医療推進に関する研修会 2019.1
摂食嚥下ネットワーク 2018.12
千葉県歯科医学会誌 2018.11
歯科衛生学会 2018.9
4)超高齢社会を支える「入れ歯」の役割について 動画⑧
講師:河原英雄先生(歯科医師、医学博士)(50分)
◇アンケート
今後よりよい事業運営を行っていくために、ご協力をお願いいたします。
→http://cda.or.jp/295
